加藤清正が持ち込み、細川忠興が熊本に根付かせた 伝統工芸品って無敵じゃないですか!?

「肥後象嵌」の店と言えば、新町にあるこちら。ただ、何と読むか分からないので、まずはそこから復習してからお店に入ります。
Lesson1
「肥後象嵌」は「ひごぞうがん」と読みます。

続いて、
Lesson2「光助」は「みつすけ」です。
みなさん、覚えましたか~?

改めて……(↑ここまでを、若干なかったことにしたいので、笑)
清正さんの指令を受けお邪魔したのは、新町にある「肥後象嵌 光助」さんです。 電車通り沿いにあり、店の前を路面電車が走る様子は、熊本の風物詩のひとつ。
写真映えもバッチリです!

こんにちは~。
誰かいらっしゃいますか~?

ここ、伝統工芸品を
売ってる店なの?

あっ、いらっしゃった! 作業中でしたか! すみません!

お顔が見えないので、
もうちょっと近づきます。

かっこいい! ダンディー!
(職人さん=ちょっと怖いイメージとは、ちょっと違いますね)

この方が、「光助」さんの4代目。肥後象嵌の職人・大住裕司さんです。早速、肥後象嵌についてお話をうかがいます。

象嵌とは、鉄地などに金銀を打ち込んで装飾を施す、日本に古くからある伝統工芸のことです。象嵌師が熊本にやって来たのは、約400年前の江戸時代と言われています。

そうじゃ、わしが熊本城築城の際に、全国から職人を集めてきたんじゃ。

清正さん、スゴいですね!

その後、文化人としても知られる細川忠興公が、職人に刀の鍔(つば)の象嵌を作らせたのが、肥後象嵌の始まりですね。

お洒落なネクタイにこだわるように、お洒落な鍔(つば)が流行っていたんですね。

そんな感じです。その頃は、細川家お抱えの象嵌師が何人かいて、その他に、うちのような一般の職人が何十人かいた、ということを聞いています。一般の職人は、キセルや鉄砲の象嵌を作っていました。

武士から、徐々に庶民にも広まっていったんですね。



元々、うちは鍛冶屋だったんです。鉄製品を作る分業制のなかで象嵌を作っていて。時代の移り変わりとともに肥後象嵌専門になりました。明治7年に雅号を『光助』として、以来その名で象嵌を作るようになったんです。

それまで専門でされていた職人たちはどうしたんですか?

明治9年の廃刀令によって刀が必要無くなったと同時に、鍔もいらなくなったんです。当時、鍔だけを専門にしていた有名な象嵌師たちは、その事を機に全員廃業しました。でも、うちは鍛冶屋もやっていたので、明治以降も、時代に沿った品を作りながら現在に至っているという事です。


肥後象嵌師になったキッカケは
スキーでの骨折!?


大住さんの象嵌師としてのキッカケを教えてください。

24歳くらいだったかなー。まあ、当時は「光助」を継ぐ気もあまりなかったので、大学を卒業して、東京で就職していたんです。その頃スキーに行った時に、全治1年の骨折をしてしまって…。

全治1年!?

1カ月の聞き間違いでは?

1年です…。それで熊本に帰って入院することに。「また東京に帰っても、会社に迷惑かけるから」と考えてそのまま実家に戻り、象嵌の道にはいったんです。

マジですか!? 骨折がなかったら継がなかったかもしれないってことですか?

分からないですね~(笑)。別に家を手伝っていたわけでもないし。というより、手伝うものじゃないからですねこの世界は。骨折した頃は、まだ景気が良くて、職人も十何人いて、結構活気があったんです。「継ぐなら今しかないかなー」と思って。

軽い…。

でも、昔から象嵌のある暮らしではありました。漆とか水銀とか、家の周りにすごいものがあちこちにありましたね。普通、漆に近寄れば“漆かぶれ”をしますよね。でも私は、漆塗りを素手でします。祖父の頃からそうでした。多分、身近に漆があったから耐性があるんでしょう。私以外の職人は、全員漆にかぶれるので、環境が影響していたんでしょうね。

英才教育!

肥後の伝統が託されたわけじゃ。


伝統の技だけじゃない。
4代目が受け継ぐのは、未来に繋がる熊本の文化

伝統工芸品を受け継ぐ大住さんだが、店内に並ぶ商品は、ネクタイピンやブレスレッド、ピアス、おしゃれな文鎮など、工芸品店というよりブティックのよう。


代によって作風が変わるということですが、お洒落すぎます!

今、熊本に象嵌師は、だいたい14・15人ほどしかいなくて…。組合を作って一生懸命やっていますが、なかなか後継者がいないんです。これは、つまり「売れない」ということを意味します。伝統だけを守っていてもどうしようもない。現代に必要のない鍔は、やっぱりいらないわけです。だから、売れるためにいろいろと工夫して、新しいものを作ったり、違う業種の方とコラボをしたり、文字盤や家紋を入れたオリジナルのものを作ったりチャレンジしているわけです。時代に沿った商品を作っていかないと、伝統工芸品は生き残れない。伝統だけじゃ無理なんです。

現実は厳しい……。


「伝統の肥後象嵌=鍔・キセル・鉄砲」。それはどうにも進化させようがありません。今の人に「象嵌ってなんですか?」と質問されて、「鍔、キセル、鉄砲です」と答えても分からないですよね?

はい!

それなら、肥後象嵌の技術を活かした、新しい工芸品を作っていこうと。

確かに、伝統工芸品は敷居が高いと感じる私たち世代でも、 アクセサリーなどの身近な物だと、興味がわいてきます。

伝統と革新。いつの時代も変化する時には必要なことじゃな。




そんな考えもあって、現在、オーダーを中心にやっているんです。

昔から肥後象嵌は一点ものじゃったな。

価値を落とすことなく、ニーズに応えてる!

ええ。メガネに時計、チェスも作ります。象嵌という工芸品が生まれた原点に戻り、一点物のオーダーでいく。これしかないんです。安いものじゃ勝負できないから、強みを活かしていかないと工芸品は生き残れません。

肥後象嵌体験も実施!
城下町の老舗は、すごく古くて新しい!?

「そうだ、せっかくだから体験していきませんか?」との言葉に、緊張しつつも「もちろんです!」とひとつ返事。これだけのお話を聞いて、自分で作る事ができるなんて貴重な体験です。上手に出来すぎてスカウトされたらどうしよう(と、いらぬ心配をする下田です)。

あ、うちは事前の予約で象嵌体験が出来るんですよ。

そういうこと!? ついでに、それを清正さんへのお土産にしちゃおう♪

仕上がりが不安すぎるぞ…。
2階へGO!

ルンルン♪

使うパーツたち。
この小さいこの黒いシルエットは……

まずは説明を聞いて、
お手本を見ながらやってみます

こちらで用意した鉄板に純金を打ち込んでもらう体験です。時間は40分~1時間位でだいたいみなさん終わられますよ。このくまモンなどの絵柄に、自由にデザインして、象嵌をつけてみてください。
ちまちま…ちま、ちまちま


海外の方にも人気の体験です。

世界に一つの象嵌が作れるから、喜ばれるでしょう! 私もがんばんなきゃ!

くしゃみ厳禁! 息を止めて……
(ぷぁあ、死ぬ!)←そんな事しなくて大丈夫ですよ(by大住さん)


では次の行程へ。地金に純金を打ち込んでください。金づちで、鹿の角を打ちながら、少しずつ金を伸ばしていきます。
コンコンと打つ…

ひたすら、コンコン……

(完全に無言に…)

手直しをしてくれるので安心

そして、1時間後…
世界に一つだけの
肥後象嵌くまモンが完成!


わーい、清正さんにお土産が出来た♪

上手に出来ましたね。この後、こちらで錆だしをしてだいたい2週間後に完成です。
ヤバッ!
清正さんに怒られる!
ま、いっか(笑)


はいはい…。


表と裏、両面のこころがけ、どれもおろそかにしてはならじ。
肥後象嵌の400年近い歴史と、受け継がれてきた技術。この両方があってこそ、未来に紡ぐための革新が出来るというもの。大住さんは、その事をしっかりと理解した上で、代々受け継がれてきた伝統工芸品に柔軟に向き合っています。表と裏、伝統と革新。どちらもおろそかにすることなく進化していくのです。
大住 裕司さんがオススメする、
近所のラストサムライ

- 毛利秀士
-
熊本城下町の町づくりにご活躍。歴史と文化を活かした取り組みを行い、地域の自治会長も務める。 広い経験と知識に基づくまちガイドが評判で、各店舗の名物も熟知されている。
TEL:096-324-4488(肥後象嵌 光助)
営業時間:まちあるきガイドは3日前までに要予約
1名500円(90分程度)
休み:不定休
席数:なし
駐車場:なし
肥後象嵌 光助
お問合せ/096-324-4488
営業時間/9:00~17:00
(土日は10:00~16:00)
定休日/年末年始
住所/熊本市中央区新町3-2-1
アクセス/J熊本市電B系統
段山町駅徒歩3分

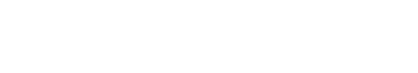
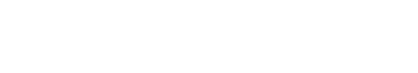

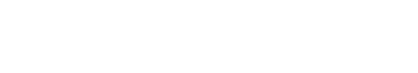
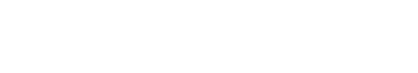
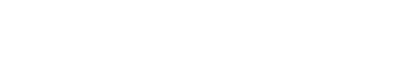
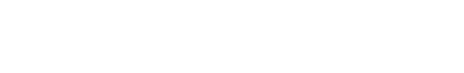




どうも! 熊本出身・愛知在住のライター・下田宣代です。久しぶりに熊本に帰ってきて最初の指令が、清正さんのお洒落グッズを調達する事って、面白すぎますね。私も初めてお邪魔する場所ということで、ワクワクしっぱなしです! いざ、新町へ!